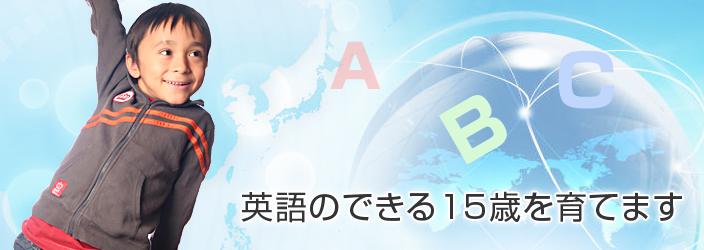8月6日 アルゼンチンの高校と共同で取り組んでいる平和学習の発表の日を迎えました。
JOY CLASS では個人での取り組み2つ、グループでの取り組み3つ発表しました。
まずテーマを何にするかを話し合い、伝えたいことを相談しました。
テーマが壮大で切り口をどこにもってくるか、心配ではありましたが、
本や資料の提示をするだけで口だしはしない!と決め、以下の2点だけを伝え、生徒の自主性を重んじることに決めました。
1,調べるサイトは信用できるサイトを選ぶこと。ウキペデイアは避けること。
2,調べた内容を発表するだけでなく、自分としてどういうアクションができるかを着地点とすること。
アクションは壮大な抽象的な内容ではなく、自分が実現可能なアクションであることが望ましい。
6月からプロジェクトのテーマを伝えていたものの、なかなか自分事として考えが及ばない人も多かったのですが、
実際7月にアルゼンチンの高校生とじかに遭い話したことで、モチベーションが急上昇しました。
日本と12時間も時差のあるはるか彼方の国の同世代の人たちが原爆に心を痛めてくれていること。
自分たちの国の歴史なのに、しらないことが多いこと。いろんな気づきがあり、どの生徒も心が動いているのを感じました。
伝えたい!知ってもらいたい!これが彼らの原動力となったように思います。
高2生を中心とするクラスの一人が課題図書で昨年読んだ「あるはれた夏の朝」を皆で読んだらどうだろう?という意見が出ました。
私も読んだことのない本でしたが、皆で回し読みをしたり、図書館で借りてきたりして読みました。
本を読んで気づいたこと、深めたい視点がそれぞれ違っていて、自分が深めたいことをさらに調べ学習をすることにしました。
そして、3日前の8月6日本番を迎えました。
教科書に出てくる本文を朗読したり、クイズ形式で現代の原子力の怖さを伝えたり、それぞれに工夫しながらも、
自分事として考えた内容の発表になりました。全ての生徒がこのプロジェクトに参加した意義、意味を深く考え、
今、自分が幸せにくらせていることへの感謝、自分たちが原爆や戦争の恐ろしさをしっかり次世代に継承することの大切さに気づいたと言っています。
アルゼンチンの高校生たちも、いろんな視点からの発表をしてくれました。
若い人たちの視点、洞察、分析力は素晴らしいものでした。
発表会を何度も経験していますが、今回の発表はより深い思いと静かな感動で胸がいっぱいになりました。
資料のresource など、Media Litercy に関してはまだまだ学ぶことが多いです。
彼らとともに学びを続けていきたいと思います。
1時間20分の取り組みを16分にまとめました。かなりコンパクトにまとめていますが、当日の様子をごらんください。